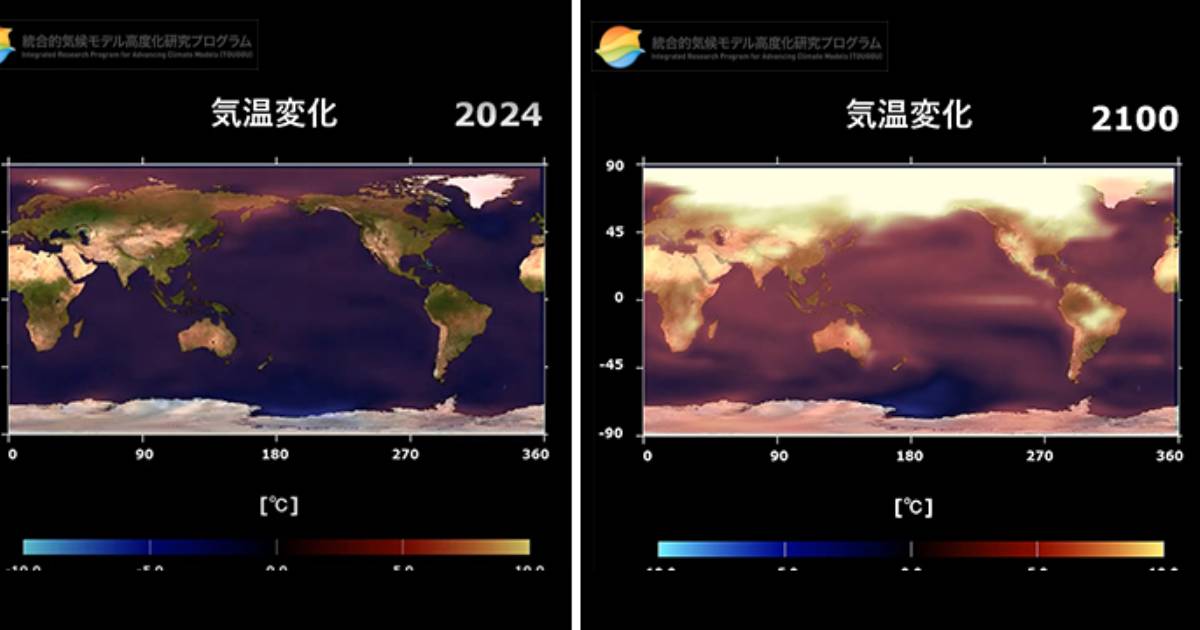25年後、日本に魚がいなくなる?国内漁業の危機的状況に専門家が警鐘「資源管理ができてない」「補助金で休んでもらった方が漁業は復活する」40年間で漁獲量は1/3に激減(ABEMA TIMES) – Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/7d121ccd77cb7e7fa1049b146d9444f1d97d83e3
https://news.yahoo.co.jp/articles/7d121ccd77cb7e7fa1049b146d9444f1d97d83e3